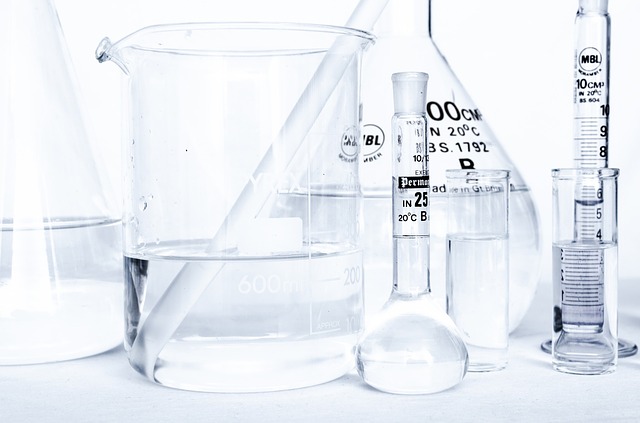はじめに
今日はいつもとトーンを変えて、私の化学メーカー勤務時代のことをお話ししたいと思います。
ドキュメンタリータッチで書いていますが、中身的には「はじめてのおつかい(新人研究員編)」です(笑)
モノづくりに携わっている方に多少なりとも親近感を持って頂ければ嬉しいです。
初のテーマは「製造技術の確立」
大学の化学科を卒業した私は、神奈川県平塚市にある三協化学という会社に就職した。この会社は富士フイルムの関連会社で、写真用化学薬品の合成を主な事業としていた。
平塚事業所には大規模な7つの工場設備に、2つの研究所が併設されていた。私は2つの研究所のうちの一つ、生産技術研究所に配属されることになった。
新人研修が終わると、私にも研究テーマが与えられた。
そのテーマは「電子写真用材料の合成技術および製造技術の確立」。
入社したての新人に任せるということで、比較的取り組みやすいテーマを選んでくれたのだろう。ターゲット化合物の構造はシンプルで、フラスコレベルでの合成手法については前任者によって既に確立されていた。だから私に与えられたタスクは工場設備でその化合物を安定的に生産可能な手法を確立することだった。
前任者の手法をトレースしたがフラスコレベルでの問題点は特に見い出せなかった。このため、工場設備での試作を行うことになった。
スケールアップは意外に難しい
フラスコで反応がうまくいったからといって、工場設備でもうまくいくとは限らない。
ラボでよく使われるフラスコは100-500mLであるのに対し、工場設備の反応釜は一番小さいものでも100L。200-1000倍のスケールの違いがある。
反応容器のサイズが大きいと、容器の外側に熱媒や冷媒を通しても、その温度が容器の中心部まで伝わりにくい。だから、反応液を十分に加熱することができず思ったように反応が進まなかったり、逆に冷却が間に合わず反応が暴走してしまったりということが起きる。
化学反応のスケールアップは意外に難しいのである。
いよいよ実機試作へ
工場敷地の東端にポツンと建っている試作専用設備(通称「T-2設備」)で私の初試作が始まった。
ターゲット化合物の合成は、N-アリール化、ホルミル化、そしてヒドラゾン化という3つの反応からなる。この3つの反応の中では、第1工程のN-アリール化が一番やっかいだった。Ullman反応と呼ばれる反応で、原料を200℃以上に加熱しないと反応が進行しない。
しかし、工場設備の中に200℃以上の反応を想定した反応釜はなかった。そこで、普段は反応には使わないT-2設備の100L蒸留釜を使って試作を行うことになった。
朝一で釜に原料を仕込み、熱媒となるオイルを循環させて釜を温める。フラスコでの実験とは違い、100Lの釜を200℃まで温めるだけでも、かなりの時間がかかる。漸く反応温度に達したのは昼過ぎ、反応が完結したのは夕方5時、それから後処理を行って、全ての作業が終わったのは夜の8時過ぎだった。
極度の緊張と慣れない作業でグッタリしながらも、一番の難所であるN-アリール化がうまくいったことに、ほっと胸を撫で下ろした。こうして私の試作1日目は終わったのである。
(つづく)
クロスリンク特許事務所からのお知らせ
クロスリンク特許事務所(東京都中央区銀座)は中小企業専門の特許事務所です。
日本弁理士会 関東会で中小企業支援の活動に9年間携わってきた「中小企業の知財」のスペシャリストである弁理士が貴社からのご相談をお待ちしています。
特許の申請にかかわらず、
- 特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録などの知的財産権の取得手続き
- 商品企画や商品開発、企業ブランディングや商品名のネーミングに関するご相談
- 原稿執筆、セミナー講師のご依頼
などのご相談をお受けしています。権利を取る前から取った後まで。一気通貫にアドバイスをしています。
下のボタンをクリックしてください。お問い合わせフォームが表示されます。